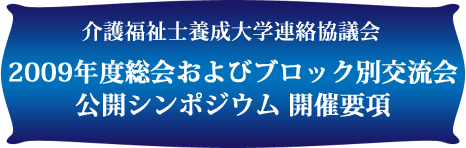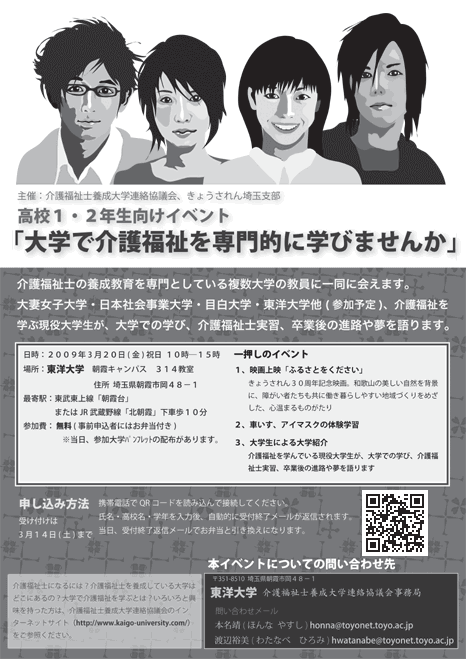「今後の介護人材養成のあり方に関する検討会 中間まとめ」に関する調査報告
2010年12月9日
「今後の介護人材養成のあり方に関する検討会 中間まとめ」に関する調査報告
介護福祉士養成施設協会基本問題検討委員会 大学部会 介護福祉士養成大学連絡協議会 宮内寿彦(十文字学園女子大学)
本調査は、本年8月に示された「今後の介護人材養成のあり方に関する検討会 中間まとめ」について、「介護福祉士養成大学の現状」を伝えていくことを目的として実施いたしました。調査期間が短いにもかかわらず、ご協力頂きました皆様に感謝申し上げます。 この調査結果は、介護福祉士養成施設協会大学部会(部会長 古川 孝順)、を通して、澤田基本問題検討委員長(介護福祉士養成施設協会副会長)へ伝えていきますことを申し添えます。 ■ 調査概要 1-1. 調査主体 ・介護福祉士養成施設協会基本問題検討委員会 大学部会 ・介護福祉士養成大学連絡協議会 1-2.調査対象及び調査方法 ・介護福祉士養成大学(14 大学)※介護福祉士養成大学連絡協議会未加入校 ・介護福祉士養成大学連絡協議会会員(正会員大学所属:54 大学)及び個人会員(6名) ※本調査では、介護福祉士養成大学所属の個人会員は正会員大学として集計 ・電子メール調査法及び郵送調査 1-3.調査時期 ・調査票の依頼時期・・・2010年11 月1日(月) ・調査票の回収時期・・・2010年11 月15 日(月) 1-4.回収結果 ※全介護福祉士養成大学回収数(68 大学中36 大学;回収率52.9%) ・介護福祉士養成大学回収数(5大学;回収率 35.7%) ・介護福祉士養成大学連絡協議会:正会員大学回収数(31 大学:回収率 57.4%)、個人会員回収数(3名:回収率 50.0%) 表1.基本属性の回答内訳
| 度数 | パーセント | 有効パーセント | 累積パーセント | ||
| 介護福祉士養成大学 | 5 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | |
| 有効 | 連絡協議会会員大学 | 31 | 79.5 | 79.5 | 92.3 |
| 連絡協議会個人会員 | 3 | 7.7 | 7.7 | 100.0 | |
| 合計 | 39 | 100.0 | 100.0 | ||
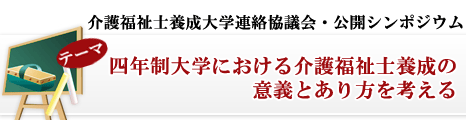 介護福祉士を養成する四年制大学は60を超えている。その一方、ここ数年、介護福祉士養成の短期大学・専門学校は減少傾向にある。相対的に大学での介護福祉士を養成することの重要性は増したと言える。しかし、そこでの人材養成・教育(あるいは研究)のあり方についての議論はこれまで十分とは言えない。大学で介護福祉士養成する意義とは何なのであろうか。このシンポジウムで、複数の大学教員・卒業生・介護実践現場のそれぞれの立場からの発言を聴き、これからの介護福祉士に求められる専門性と養成教育のあり方を大いに議論したいと思う。
介護福祉士を養成する四年制大学は60を超えている。その一方、ここ数年、介護福祉士養成の短期大学・専門学校は減少傾向にある。相対的に大学での介護福祉士を養成することの重要性は増したと言える。しかし、そこでの人材養成・教育(あるいは研究)のあり方についての議論はこれまで十分とは言えない。大学で介護福祉士養成する意義とは何なのであろうか。このシンポジウムで、複数の大学教員・卒業生・介護実践現場のそれぞれの立場からの発言を聴き、これからの介護福祉士に求められる専門性と養成教育のあり方を大いに議論したいと思う。
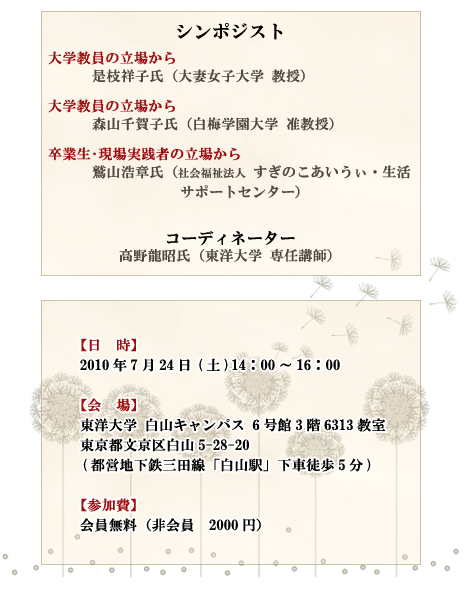

 介護を学ぶことに関心のある高校生のみなさんに、「大学で介護を学ぶ」ことのイメージをふくらませていただく機会として、下記のようなイベントを企画しました。
メイン企画として、今、高齢者の介護分野で注目されている“フットケア”(足の皮膚や爪のケアを行うことで高齢者の生活を支援していく方法)の第一人者の先生をお招きし、それをみんなで楽しく勉強しようと思います。さらに、大学で介護を教えている教員や在学中の大学生たちと交流をする時間ももちますので、高校生のみなさんの疑問や不安に応え、大学生活や大学での授業を身近に感じていただくことができればと思っています。
どうぞお気軽にご参加ください。
介護を学ぶことに関心のある高校生のみなさんに、「大学で介護を学ぶ」ことのイメージをふくらませていただく機会として、下記のようなイベントを企画しました。
メイン企画として、今、高齢者の介護分野で注目されている“フットケア”(足の皮膚や爪のケアを行うことで高齢者の生活を支援していく方法)の第一人者の先生をお招きし、それをみんなで楽しく勉強しようと思います。さらに、大学で介護を教えている教員や在学中の大学生たちと交流をする時間ももちますので、高校生のみなさんの疑問や不安に応え、大学生活や大学での授業を身近に感じていただくことができればと思っています。
どうぞお気軽にご参加ください。